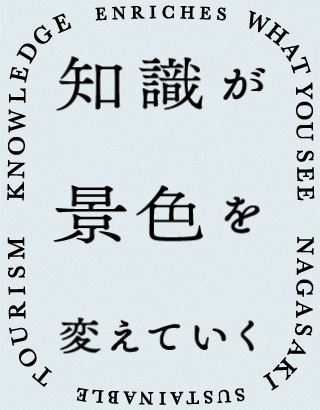

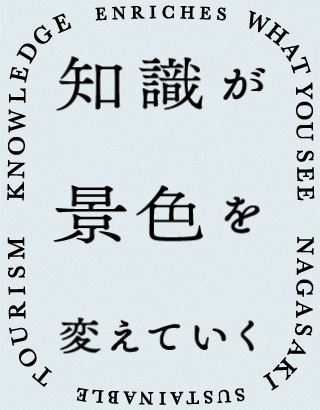

生き方は、
風にまかせない。

鮮やかな青白赤の3色は揚げた時に映える
17世紀、オランダ船に乗っていた
インドネシアの人々から
伝わったと言われる長崎の凧(たこ)、ハタ。
長崎の三大行事とされるハタ揚げに
欠かせないハタ作りと
ハタ揚げを体験します。

全てのパーツが職人の技術による手作り
青・赤・白の主に3色でデザインされるのは、オランダ国旗の配色を取り入れているから。その柄の数は300種以上とも言われます。「揚げる」というハタのもつ行為が験かつぎに使われるため、長崎ではお祝いや子供の誕生などで贈り物としても使われてきました。

まず、あらかじめデザインされた飾り用のハタに竹を糊付けして組み立てます。その後、初心者でも揚げやすい形のハタに、ペンを使って自由に絵を描き、天気がよければすぐそばにあるハタ揚げの聖地、風頭公園でハタ揚げを楽しみます。
ハタづくりをする間、生粋の長崎人、小川さんのハタに関する話や長崎の歴史について、軽妙なトークが場を和ませます。手作りのハタに囲まれた空間は、この地で守り継がれている文化そのものです。

しっぽがあるほうが安定するが合戦には不向き
飛ばすのは初心者向けのハタなので簡単に風に乗る

ハタを組み立てたり絵を描いたり

ハタづくり職人の3代目。竹の切り出し、和紙の染色、切り抜き、組み立て、凧糸(ビードロ)づくりまで全ての工程を一人で行う。小学生の頃からハタ揚げ大会で優勝する腕前。
すべての工程が手作りだから、好みのハタをオーダーメイドでも製作できます。


長崎ではハタどうしを絡ませて相手の糸を切って落とすハタ揚げ合戦が行われます。しっぽのないハタは動きが不安定。だからこそハタを上下左右に自在にハタを操ることができ、勢いよく相手のハタへと向かわせてビードロと呼ばれるガラスを練り込んだザラザラした凧糸を切り落とします。春には各地から長崎に腕自慢が集まって大会が行われ、日本一を決めます。
400年以上もの間、長崎で受け継がれてきたハタ。つくる人がいなくなれば、揚げることはできません。つくる人、揚げる人、どちらもいれば、どちらも栄える。腕も上がる。ハタの奥深さを知ることが、その一助となります。

小川さんがまだ20代前半の時、父である先代は病に倒れ、技を継承する間もなく代替わりしました。「数をこなせば自然と手が動く」父に言われたこの言葉を信じてハタを作り続けました。父の残したハタを見ながら。ハタづくりの技を受け継ぐには、何よりハタ揚げが大好きであることが大切。ハタ揚げがうまくなければ「勝てるハタ」を願うオーダーメイドにも応えられないのです。

風の強さに応じて骨組みとなる竹の削り方を変える


小川ハタ店
住所:長崎市風頭町11-2
営業時間:9:00-17:00
駐車場:あり





