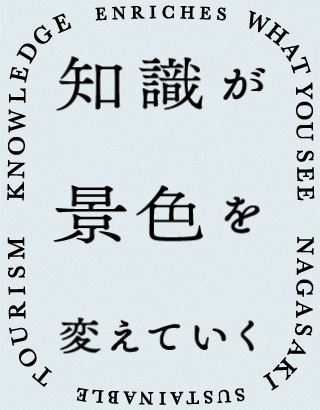

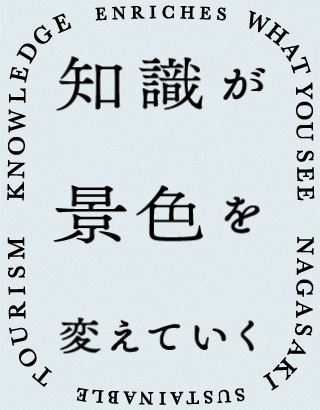

進む崩壊を食い止める
力を求めて

端島、通称軍艦島。
1868年、グラバーが
英国人技師モーリスを呼び寄せて洋式採炭法を
導入した高島炭坑から遅れること約20年。
三菱に譲渡された良質の石炭が採掘される端島炭坑は
出炭量は高島炭坑を抜くまでに成長しました。

最高品質の石炭が採掘される端島では多くの人が働きました。7度の埋め立てが行なわれた島には日本初の高層鉄筋コンクリート造アパートが建ち並び、南北に480メートル、東西に160メートル、周囲1,200メートルの島の人口は、最盛期には5000人超。人口密度は東京都の17.5倍で、世界一と言われていました。1958年当時、テレビの普及率が10%の日本でほぼ100%テレビを保有していました。

この風景を後世に残すために上陸する
上陸ツアーは、石炭産業が隆盛だった当時の暮らしを感じることが一つの目的です。でも、それだけではありません。崩壊が進む建物と、保存のための補強工事がごく一部でしか進んでいない軍艦島の現在を見てもらうことによって、この島を後世に残す活動に賛同する人を増やしたいという想いがあるのです。
軍艦島コンシェルジュは、崩壊が進む軍艦島の建物を補強し、保存していく活動に入場料やグッズの売り上げの一部を寄付しています。また他にも、資金調達に向けて様々なアイデアの実現に動いています。

崩壊が進む建物は一部で補強工事が行われている

建物はかつてここに暮らしがあったことを無言で物語る

まだツアーがなかった2000年頃、初めて上陸した軍艦島の、言葉では言い表せない迫力や空気感に衝撃を受けて以来、保存活動を推進。長崎の将来を考え、行動し続けるトップランナーの一人です。
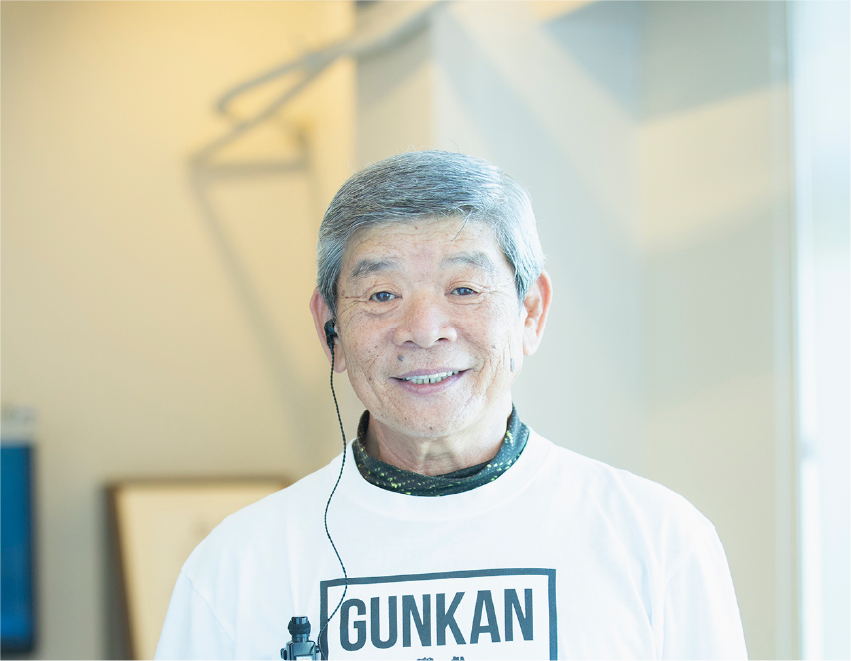
元島民で、軍艦島デジタルミュージアムでは自身の体験を交えて島の生活を説明してくれます。中学一年まで過ごした軍艦島での暮らしのすべてを知っていて、どんな質問にも気さくに答えてくれます。
精巧な模型や資料、VRや5D映像まで駆使する館内コンテンツ


ミュージアムと上陸をどちらも見ることで島の見え方が変わる
「廃墟が世界遺産になるわけがない」と言われながら活動を続けました。「長崎に新たな観光コンテンツをつくる」そんな使命感のもとに活動を続けた一人が久遠さんです。2014年、端島閉山40周年イベント「大端島展」を長崎県美術館で開いたことで元島民代表の方をはじめとする協力者が増え、軍艦島を世界遺産にする機運が高まりました。翌年、世界遺産に登録。初めて島に上陸してから15年の月日が経っていました。
天候により波が高いと上陸できない日もある上陸ツアーの他にも、軍艦島を知る場所を。大端島展をはじめとしてコツコツと収集し続けてきた元島民のみなさんの写真や映像は、最新の技術を駆使して軍艦島デジタルミュージアムで当時の暮らしを誰もが体感できるコンテンツとなりました。端島で生まれ育ったガイドさん達の話や、バーチャルな体験を通して、上陸する以上のリアルな軍艦島の暮らしを体感できます。



屋外デッキで解説を聞きながら軍艦島へ向かう
軍艦島デジタルミュージアム
住所:長崎市松ヶ枝町5-6
営業時間:9:00-17:00
駐車場:近隣駐車場(有料)多数あり
軍艦島コンシェルジュ(軍艦島上陸・周遊クルーズ観光船)
住所:長崎市松ヶ枝町5-6(クルーズ観光船受付場所)
運航情報:1日2便運航
午前便 9:00-受付 10:10-乗船開始 10:30-出航 13:05頃帰港
午後便 10:30-受付 13:20-乗船開始 13:40-出航 16:10頃帰港
駐車場:近隣駐車場(有料)多数あり





