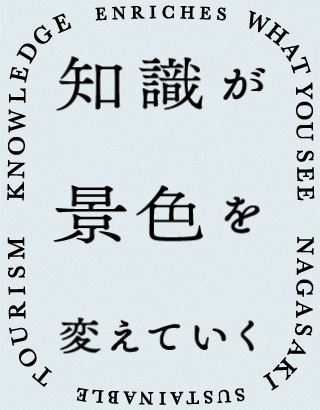

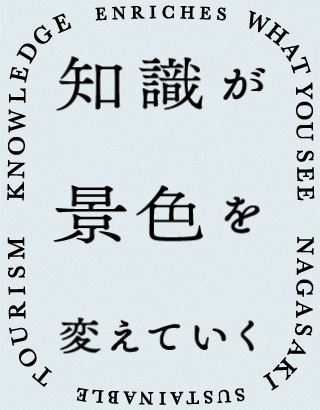


Plan
新たな出会いがある限り、
人の営みは受け継がれる。
日本において初めて蒸気機関を用いた
近代的石炭採掘が行われた長崎。
採掘された石炭は産業発展に欠かせない
鉄の製造に使われました。
長崎には軍艦製造のための製鉄所が置かれ、
造船業発展の礎となりました。
それはまた、原子爆弾が投下される
理由の1つとも言われています。
ヨーロッパと中国の文化を受け入れて混じり合い、
独自の進化を遂げた、
日本でもここ長崎にしかない文化や風習。
長崎の発展の歴史と悲劇を追体験しながら、
ここに暮らす人々や文化・風習に触れ合う
サステナブルツーリズムです。
1
一人の野心ある商人が 降り立った港町
外国人居留地として造成された南山手地区の中でも、長崎港を見渡す丘の上に立つ邸宅。現存する日本最古の木造洋風建築に住んでいた実業家トーマス・B・グラバーを知ることで、長崎発展の歴史の礎を知ります。
2
良質な石炭と 刀匠の技が生む
長崎市南西部。炭鉱のある島々に近い半島の入江にある小さな漁師町が 蚊焼(かやき)庖丁の町です。かつて30ほどあった鍛治工房も、残りわずか。 刀鍛冶から100年以上も受け継がれてきた庖丁づくりの技を体験します。
3
進む崩壊を 食い止める力を求めて
端島、通称軍艦島。1868年、グラバーが英国人技師モーリスを呼び寄せて洋式採炭法を導入した高島炭坑から遅れること約30年。三菱に譲渡された良質の石炭が採掘される端島炭坑は出炭量は高島炭坑を抜くまでに成長しました。
4
平和の種をまき続ければ、 いつかどこかで花が咲くはず。
1945年の原爆投下による被害の惨状をはじめ、原爆が投下されるに至った経過や、原爆の被害、人々の苦しみ、街の復興の様子や、語り継ぐ意味を知るため、爆心地周辺を訪れます。
5
受け継ぐとは、 更新すること。
寺町と呼ばれる、17世紀から寺社が建ち並ぶ町の一角に1813年に生まれた一力(いちりき)で、女将や仲居、料理人といった人々とのコミュニケーションを取りながら、長崎検番の芸妓が披露する踊りや音曲を楽しみます。
6
自然とあいさつが生まれる 狭い路地で
市街地の南に位置する南山手地区。ここは日本が開国した後、外国人が居住を許された場所です。平地の少ない長崎は産業発展とともに人口が増え、宅地を求めて山の上へ上へと移り住んで、斜面地は人間の丘と言われるほどでした。
7
生き方は、 風にまかせない。
17世紀、オランダ船に乗っていたインドネシアの人々から伝わったと言われる長崎の凧(たこ)、ハタ。長崎の三大行事とされるハタ揚げに欠かせないハタ作りとハタ揚げを体験します。
8
誰もがちゃんぽんを 長崎の思い出にできるように
店主が中国人留学生に安くて栄養があるものを食べさせたいと作ったちゃんぽん発祥の地、四海樓。その向かいの地で生まれたのがヴィーガンやベジタリアン、アレルギーに対応したちゃんぽんと皿うどんです。